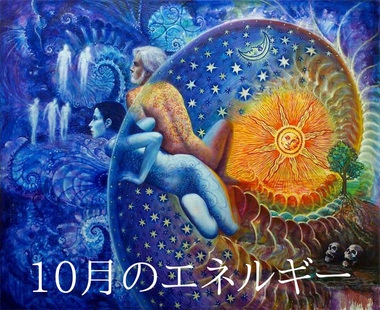=べネゼィラに現れた巨大な光の十字架=
人類の秘法(道=真理)その鍵がどのように伝えられてきたのでしょうか、正しい宗教の経典にはその極意が伝承されてきましたが、時代が下るほどに異端が跋扈しその解釈は有名無実となってしまいました。
老子には元始(ゲンシ)、孔子には項屣(コウモ)、釈迦には燃燈佛(ネントウブツ)が秘伝の法灯を伝授しました。
老子は、道徳経、第一章の中で「道可道、非常道、名可名、非常名、無名、天地之始、有名、万物之母、故常無欲、以観其妙、常有欲、以観其竅、此両者、同出而異名、同謂之玄、玄之又玄、衆妙之門、」
【解釈】:道というは、常にいうその道ではない。その名でもない、名が無いが、「天地の始め」であって、その名をあえて、「万物の母」という。つねに無欲である故にその妙を観る。「天地の始め」であり「万物の母」この両者は、同じ根源から出ているが、名を異にしている。これを玄(玄関)という。玄の中の玄を、あらゆるものを生み出す神秘の中の神秘、それを衆妙の門という。(衆妙の門:多くの人々に付与された命の微妙な出入り口)、玄妙不可思議なメスの陰門(ほと)は、これぞ天地を産み出す生命の根源、と解釈してます。
※ 「玄関」と言う日本語の漢字は、中国では使われていません。仏教の経典の中にしか使わない聖なる言葉を日本語では人の出入りする「戸」のある場所、聖なる「玄関」と言う言葉を日常に使っています。
清静経では、「大道は無形にして天地を成育し、大道は無情にして、日月を運行し、大道は無名にして万物を長養す。吾その名を知らず。強いて名付けて道という。」
※老子は道徳経・清静経・黄庭経の三経を遺しています。
【解釈】:大道は本来形象はないが、よく天を生じ、地を育てることができる。本来感情はないが日月を運行することができる。本来名称をもって表現できないが、天地間の万物を養育することができる。私自身、その名前を知らない。それで強いて道と名付けた、と伝えています。
釈迦は、弟子スプーティに「解脱に至る道(真理)は、どのような道でしょうか。」と問われ、「解脱に至る道によって解脱を得るのではない。また道でないものによって解脱を得るのではない。スプーティよ、解脱がそのまま道であり、道がそのまま解脱である。一(真理)を得ることが、その一切である。」と答えました。
また、摩訶迦葉に法灯を伝える時「吾に正法眼蔵あり、涅槃の妙心、実相無相にして微妙の法門、不立文字、教外別伝、これを摩訶迦葉に附嘱す。」「粘華微笑、玄嚢鼻直」と説き、正しい法が眼の蔵(老子:谷神)にある。それは涅槃(天国)へ通じる道で、あるといえば無い、無いようである、微妙な法門である。文字を立てず(文字に表すことはない)、教えの外に別に伝える(誰にでも教えるものではないし、教えるというものでもない)、一人から一人に単伝独授するもので、これを摩訶迦葉に附嘱(一指相伝)し、その機微を顕しました。そして鼻を捻って微笑し(粘華微笑)それは鼻の玄嚢の直すぐ上である、と記しました。
達磨大師は釈迦以来の四諦句として「教外別伝・不立文字・直指人心・見性成仏」とその奥義を禅宗に遺されました。一つ一つの四字成語をよくよく観察してみて下さい。どの経典でも、これは名のつけようもなく、経典の文字をいくらあさっても解るものではないと伝えられています。
一指相伝:一を指して相伝える、直指人心:直かに人の心を指す、など似たような表現ですが、ではそれが具体的に何を意味するのかと考えると曖昧になります。つまり求めなければ得られないものの特徴です。

また、面目と言う言葉は、顔面の目と言う意味であり、すなわち「大元である」という意味ですが、熟語には「面目一如」一の如く、「面目一新」一に新(親)しむ、「面目躍如」躍するが如く、「一」に関することでそれによって改まること飛躍(脱皮)するとは…、このように日常の様々な言葉の中に「道:真理」は隠されています。
この「道」は、無形無相、無声無臭で、見ることも聞くことも嗅ぐことも触れることもできません。これが道の実体です。
イエスは、「わたしは道であり、真理であり、命である。だれも私(道)によらないでは、父のみもとにゆくことはできない。」 (ヨハネ伝第14章)と言いました。
※ イエスの墓が青森県三戸郡新郷村大字戸来にありますが、地名の「三戸」「戸来」あるいは「戸来人」などの「戸」の由来について論語の中で次のように解釈しています。
雍也第六:子曰誰能出不由戸何莫由斯道也
解釈:子曰く、誰か能く出づるに戸に由らざる。何ぞ斯の道に由ること莫からむ
真理を得ていない場合は次のように教訓的な解釈になります。
「誰か外に出るに戸によらないものはない、どうして、(生きるに)この道によらないことがなかろうか。普通戸の無いところから出入りすることはなく、人は、無意識的に戸を用いる。道路も、無意識的にそこを通るが、もとからあったものでなく、人々が往来するから道路となったものである。道路には通る人々により、悪しき所に通じるものも、善き所に通じるものもある。道とは、ここでは、人が生きる道のことであるが、さまざまな道がある。無意識的に生きているのかもしれないが、先人の道を辿っているものである。(周公のごとく)生きた人の道(斯道)によるべき、・・・」
孔子が伝えているのは「人間の魂はどこから来てどこへ往くのか、この戸による・・・」つまり、元きたところに帰る道のことでした。
神は、イエスによって「道であり、真理であり、命(性命=霊)」ものを証するために、十字架で磔の機会を与えました。この時の場所は「ゴルゴダの丘(しゃれこうべの丘)」でした。つまり人の頭の部分です。そしてイエスと共に2人の盗人が処刑されました。三人が同時に磔になりました。
汝姦淫するなかれ”と言いますが、姦淫の源は目にあります。目で色を見ることで心が動じ罪を犯します。つまり左右両目は磔になった2人の罪人で比喩し、イエスは真中の十字架で〝私は真理である“ことを比喩しました。
また仏教の「如來」は、済いとは「菩薩が來るが如し」と言う意味に使います。この「來」と言う文字は「十」の字に「人」と言う文字を3人を書いた字です。つまり十字架に3人が磔になったことと同じになります。
如=女の口=玄牝之門(老子道徳経で“玄なる牝の門”と表現)
來=十(十字架)に从(罪人が2人従う)もうひとり、「人=キリスト」が真ん中にいて十字架に人が3人、3っの目を意味していました。

そして「戸」と言う文字について、聖書の中で「戸をたたく」と言う真理に関する機密の表現がありますが、「戸」の「一」の字を取ると「尸」(しかばね)と言う字になります。「一」は「点」の伸びた形で、「一なるもの」の意味です。つまり真理の表現です。「尸」が「一」を得て「戸」になる、つまりこの「戸」が「真理」を表現しています。京都の大文字焼きの「大」の字も「人」が「一」を得て「大」になる、やはり「一」が真理であることを継承しています。
キリストの墓がある「三戸」「戸來」の地名については、東北方面の方はご存知のように青森県には「一戸」「二戸」と言う地名があり、キリストの足跡が秘められていると思われます。
「戸來」は「如來」と同じ意味で、そのときがくれば十字の秘密が公開され、真理が得られることを印しています。キリストが日本に、しかも東北に来た(さらに南米に向かったと言う説もあります)ことの意義はやがて歴史の真実として明かされ、世界がひとつになり、宇宙とつながる史実となってきます。聖人はそのために足跡を残すべく天命を担っていました。
昨今、次第に歴史の真実が明らかになってきていますが、「真理」に基づいて歴史が明らかになるのはこれからです。エジプトも中国もどの古代文明もすべて十字などの形象で顕した「真理」を探求する歴史そのものでした。天のデザインは細微に渉っています。



 小泉進次郎氏(2017年8月20日撮影)
小泉進次郎氏(2017年8月20日撮影)

















 両院議員総会を終えて記者会見する民進党の前原誠司代表=28日午後、東京・永田町の同党本部(時事通信)
両院議員総会を終えて記者会見する民進党の前原誠司代表=28日午後、東京・永田町の同党本部(時事通信)
 ペルーのイカの石に描かれた「星を見る人』
ペルーのイカの石に描かれた「星を見る人』 





 大異変前のエーゲ海大異変後のエーゲ海
大異変前のエーゲ海大異変後のエーゲ海 ユーカラ戦争地図(『謎の新撰姓氏録』徳間書店刊)
ユーカラ戦争地図(『謎の新撰姓氏録』徳間書店刊)  東日流地底城(日本探検協会調査)
東日流地底城(日本探検協会調査)  アンリ・ロートが「火星の大王」と名づけた太古日本のアラハバキ神(アルジェリア・タッシリ)
アンリ・ロートが「火星の大王」と名づけた太古日本のアラハバキ神(アルジェリア・タッシリ) 入古のヴィマナを形どった工トルリアの古墳
入古のヴィマナを形どった工トルリアの古墳 太古の秘密を隠した口―マの丘
太古の秘密を隠した口―マの丘
 鯨をつかむ北米インディアンの伝説の鳥サンダーバード
鯨をつかむ北米インディアンの伝説の鳥サンダーバード 中世のゲルマン人と中国人が想像した『山海経』の怪物の一部
中世のゲルマン人と中国人が想像した『山海経』の怪物の一部
 「空飛ぶ蛇」「龍」とよばれた葉巻型宇宙船その内部構造
「空飛ぶ蛇」「龍」とよばれた葉巻型宇宙船その内部構造